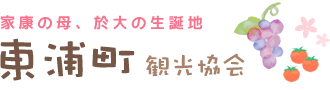日本一と称された「生路の三白」
東浦町は、古くから塩づくりや砂糖づくり、織物業で栄えた地域です。平安時代の『延喜式』や『和名類聚抄』に登場する「生道塩」は、現在の生路で採れた塩とされ、江戸時代には白砂糖の産地としても知られていました。昭和には織物産業が隆盛を極め、都市銀行の支店が置かれるほどでした。こうした歴史を伝える検地帳や古文書も現存し、地域の産業と暮らしの歩みを今に伝えています。
時代とともに息づいた、東浦の3つの白。その物語をご紹介します。
1. 平安の都・東寺に選ばれた、東浦が誇る伝説の塩「生道塩」
 塩造りの神を祀る伊久智神社
塩造りの神を祀る伊久智神社 尾張名所図会に見る生路塩
尾張名所図会に見る生路塩平安時代初期にまとめられた法令集『延喜式』には、「生道塩(いくぢしお)」という固有の地名がついた塩が記されています。これによると、生道塩はワカメなどとともに、東寺(教王護国寺)の諸尊に供えるため、尾張国から貢納されたものでした。
この法令は、享保8年(1723)に発刊された木版本を底本としています。そこにはこのように記されています。
「生道塩読云イクチ堅塩也大如大瓮元一顆搗得塩一斗許生道尾張国郡里名也」
生道塩をイクチと読み、堅塩である。
その大きさは大瓮〔おおもたい=水や酒を入れる大きな器〕ほどで、
もとは一塊の塩を搗(つ)くと、一斗〔約18リットル〕ほどの塩が得られる。
生道は尾張国の郡の里の名である。
この生道塩については、なぜか他の資料には見られません。しかし、地名を冠した珍しい名称であることや尾張に関わるものであることから、江戸時代以降、尾張の学者たちの関心を集めてきました。
『延喜式』に記されている塩の名称には、「石塩」「破塩」「堅塩」のように性質や形状を示すもののほか、「淡路塩」「紀伊塩」のように地名を冠するものがあります。これらと並べて考えると、「生道」もやはり地名であり、東浦町の「生路(いくじ)」が中世には「生道郷」と呼ばれていたことは確かです。
また、生路村には近世においても塩田や製塩施設が存在していました。こうした背景から、「生道塩」の「生道」は、現在の生路を指すものであると考えられています。
塩つくりの証拠資料
東浦町内の各区の公民館などに保管されている区文書の中に、「汐浜野帳」や「生路村塩浜検地帳」といった記録があります。
「野帳」とは、検地の際に現地で一筆ごとに記録した持ち主や面積などをまとめた手帳を清書したもので、「汐浜野帳」には32人の名前が記されています。また、『寛文村々覚書(かんぶんむらむらおぼえがき)』には、塩浜の面積として「1町7反8畝25歩」との記載があります。
一方、「生路村塩浜検地帳」には、30人の名前とそれぞれの塩浜の面積が記されており、地方吟味役の大塩藤八および鳴海代官の酒井七左衛門の名も見えます。
享和元年(1801年)には塩浜全体の再検地が行われ、総面積は「2町3反5畝26歩」と記録されています。
このような文書の存在からも、「生路塩」は現在の東浦町生路で実際に生産されていた塩であることが裏付けられています。
2. 生路で作られた白砂糖は将軍家にも献上された名産品
安永4年(1775年)に名古屋の医師が記した『安永本邦萬姓司記』には、尾張藩に関わる名地・名人・名物が紹介されています。
それによると、尾張藩内外随一の富裕者は、鳴海の酒造家・下郷五郎右衛門であり、東浦では、藩都外二番目に緒川の塚本源左衛門、都外三番目に村木の浜島惣介という、いずれも酒造家が名を連ねています。
また、諸名物の紹介の中には、生路の塩と砂糖も挙げられています。砂糖の産地としては、生路村の原田喜左衛門(はらだ きざえもん)が紹介されています。
同じ頃、内藤東甫が著した『張州雑誌』においても、生路村の項で砂糖が取り上げられています。それによると、甘蔗(さとうきび)の栽培は、享保年間に将軍・徳川吉宗が琉球から種を取り寄せるよう命じたことに始まるとされています。
甘蔗から砂糖を製造する技術は、江戸時代中期には薩摩をはじめとする九州地方でかなり普及していました。しかし、当時生産されていたのは主に黒砂糖であり、白砂糖は中国からの輸入に頼っていたのが実情でした。
 神後院にある原田喜左衛門の墓
神後院にある原田喜左衛門の墓 尾張名所図会に見る白砂糖造り
尾張名所図会に見る白砂糖造り(1) 初めて白砂糖を造った原田喜左衛門
尾張藩の儒者松平君山が長崎の人より砂糖の製法を学び、知多浦の温暖さと原田氏の力量とに注目して、享保20年(1735)それを伝授した。他にも大野村の惣右衛門(そうえもん)と平島村の安右衛門(細井平洲の兄)に砂糖作りを勧めた。原田家の製品は舶来品にも勝る上品で、将来は尾張国第一の産物になるということであった。原田家は代々製塩を家業とし、酒造業も営んでいた豪家であった。新産業に乗り出す企業家精神に富む一方、尾張藩の代表的な知識人との交際があり、その人脈が利用できた。喜左衛門は庄屋を勤め、家族8人の他牛1匹と下人5人.下女4人を召抱えて、盛大な営業ぶりがうかがわれる。喜左衛門は、安永10年3月、77歳で死去しました。
(2) 将軍家への献上品「三盆砂糖(さんぼんざとう)」
この原田家の砂糖は、尾張徳川家から将軍家への献上品になっていた。始まりは宝暦7年(1757)で、毎年11月に「三盆砂糖」の名をつけて、杉曲げ物に詰めさらに桐箱に納めて献上された。
献上品は300匁余(約1.1㎏)であるが、原田家からは1貫350匁(約5㎏)も差し出させ、これを江戸の上屋敷でお菓子師が精選して調製した。なお、原田家は尾張藩主へも献上している。尾張藩は有望な産業関係者に御貸付金として投資し、その一方で藩の御蔵物に指定して販路拡大に協力していた。
御蔵物とは藩が年貢として収納し大都市市場で換金する物資。しかし、砂糖生産は周辺農民を巻き込む新産業にはならなかった。
安政元年(1854)になって孫の代の原田家は、すでに砂糖製造を休業し、家屋敷も借金のかたに取られて借地に住んでいた。
こうして砂糖の製法は、親の代限りで伝授が絶えたという。
天保13年(1842)刊行が始まった代表的な農学書「広益国産考」では、甘蔗(さとうきび)栽培が讃岐など各地に適地を選んだ農村工業的な大量生産が始まったことで、原田家の砂糖事業は立ち行かなくなったようであるとしている。
3. 東浦を支えた綿織物
かつて東浦の一時代を支えたと言っても過言ではないのが織物業です。その繁栄を物語るように、生路には都市銀行である「東海銀行」が、昭和25年(1950年)8月7日から昭和44年(1969年)9月8日まで営業していました。
現在の喫茶店「ショパン」の隣にはかつて織物会館があり、そのさらに隣の木造モルタル仕上げの建物には、当時23名の行員が働いていたといいます。
しかし現在では、東浦町で織物業を生業としている家は、生路に1軒を残すのみとなっていましたが、その1軒も令和3年(2021年)4月に廃業しました。
かつて織物工場が建ち並んでいた跡地の多くは住宅に変わり、一部はスーパーやパチンコ店(すでに廃業)、ゴルフ練習場、病院などへと姿を変えました。特徴的だった「のこぎり屋根」の建物も、今ではほとんど見られなくなっています。
(1) 副業からスタートした綿織物
明治37年(1904)頃から、豊田佐吉が発明した動力織機が導入され、本格的な織物工場ができ始めた。
外国製の織機は1台数百円もしたが、佐吉の動力織機は1台93円であった。
明治時代には、東浦の5地区にそれぞれ1軒または2軒の工場があった程度だったが、大正時代に入ると、生路地区に織物工場が多く建てられ、織物業の中心地となった。あわせて紡績工場も多数設立された。
(2) 昭和時代の繊維産業の盛衰
戦前の昭和12年(1937)をピークとして、知多地方、そして東浦町は全国屈指の繊維産地として黄金時代を築いた。しかし、戦争による被害は甚大であり、復興には大変な労苦を伴った。それでも戦後には、他の産業や地域に先駆けていち早く息を吹き返し、10年を待たずして戦前を上回る繁栄を遂げた。
だが、昭和30年(1955)頃からは、合成繊維の登場や人手不足の深刻化、発展途上国の繊維自給率向上といった構造的な変化に加え、好不況の波やオイルショックといった厳しい社会情勢の中で、並々ならぬ苦労を重ねながら今日に至った。
(3) 戦後の復興
戦後、繊維産業は軍需産業ではなく、戦勝国への賠償を可能にする産業として、経済再建の先駆けとなる役割を担った。供出台数の1/10の復元が許可され、町内業者の約半数が再出発を果たした。
昭和24年(1949)には、東浦町で最初の紡績会社2社が創設され、町内各地でも続々と創業が始まった。
「ガチャ万」を生んだ混乱期を経て、1ドル360円の公定為替レートが設定されたことで経済社会は大きく変動。昭和25年(1950)春には製品価格が暴落し、繊維業界は恐慌状態に陥った。
(4) 繁栄と衰退
昭和30年(1955)当時、知多地方の繊維工場は半島の東岸部、特に半田と東浦に多く分布していた。
東浦は統計上、大府と同一地域として集計されているが、その約9割は東浦に属している。
東浦町の中でも、生路地区は工場数・設備数・平均設備台数において他市町比べてずば抜けた存在であった。
昭和30年代後半に入り、日本経済は高度経済成長の波に乗り、各分野で活発な活動が展開されたが、繊維業界は構造的不況にあえいでいた。繊維業は典型的な中小企業産業であり、所得向上に見合うだけの生産性の向上を実現できなかった。
さらに、昭和34年9月26日の伊勢湾台風による被害は甚大であり、織機の多くが約3週間にわたって潮水に浸かったままとなった。年末までに9割が暫定復旧されたが、被害の大きさは深刻であった。
| 東浦の工場数(軒) | |
|---|---|
| 昭和23年 | 64 |
| 昭和32年 | 165 |
| 昭和47年 | 127 |
| 昭和48年 | 168 |
| 昭和53年 | 137 |
| 昭和60年 | 105 |
| 昭和62年 | 80 |
| 平成5年 | 74 |
| 平成8年 | 40 |
| 東浦の織機台数(台) | |
|---|---|
| 昭和23年 | 6861 |
| 昭和32年 | 18038 |
| 昭和47年 | 14964 |
| 昭和50年 | 12403 |
| 昭和52年 | 13216 |
| 昭和56年 | 9480 |
| 昭和60年 | 8226 |
| 昭和64年 | 6268 |
| 平成8年 | 2331 |
(大府を含む数字)
昭和40年代に入ると、織機の老朽化や生産性の低下、労働力不足の深刻化、コスト上昇などの構造的問題が顕在化した。
昭和42年(1967)には「特定繊維工業構造改善臨時措置法」が制定され、それを契機に構造改善事業に着手した。設備の近代化、品種の転換、市場開拓などの施策を展開し、7年にわたって巻き返しが図られた。
昭和48年(1973)には、朝鮮戦争特需に次ぐ好況期が到来し、工場数は一気に41工場増加した。
しかし、オイルショックの影響で昭和49年以降一転して長期不況に突入し、コスト高によって国際競争力は著しく低下した。これにより繊維業界は構造不況に直面し、整理倒産も相次いだ。
その後、昭和52年から4年間にわたり、過剰設備の30%を対象とした共同廃棄事業が実施された。さらに昭和60年からも、3年間にわたって同様の設備廃棄が行われた。
工場の規模
| 織機台数 30台未満 | 20%~30% |
|---|---|
| 織機台数 30~100台 | 40%~60% |
つまり7割~8割は零細規模
(5) 5,700人を数えた従業員
 機屋全盛時の生路
機屋全盛時の生路
(昭和27年頃)
戦前の労働力は、地元出身者が50%を超え、不足分は三河の山間部や渥美郡から、さらに足りない場合は近隣県からの雇用に頼っていた。
昭和20年代から30年代初めにかけては、工場数・織機台数の急増に伴い、従業員数も急増した。ピークは昭和32年(1957)で、5,700人以上の雇用を記録している。
しかし、平成8年(1996)にはその数は196人にまで減少した。
職種の特性上、従業員の7〜8割は女性であった。
出身地は年を追って遠隔地へと広がり、昭和26年(1951)には鹿児島・宮崎からの求人が始まり、昭和30年代には九州全域にまで拡大した。
昭和39年(1964)の東浦町における新規就職者805人のうち、宮崎・鹿児島・大分の3県出身者が508人(約72%)を占めた。女子にいたってはその割合は90%を超えていた。
しかし、昭和35年(1960)をピークに求人環境は厳しくなり、中学卒業者の数も徐々に減少した。昭和40年代に入ると、まさに「金の卵」と称されるようになった。
従業員の推移
| 昭和28年 | 2,605人 |
|---|---|
| 昭和29年 | 3,629人 |
| 昭和32年 | 5,721人 |
| 昭和40年 | 3,306人 |
| 昭和46年 | 2,155人 |
| 昭和47年 | 1,558人 |
|---|---|
| 昭和61年 | 848人 |
| 昭和62年 | 683人 |
| 平成8年 | 196人 |
(6) 求人難と定着対策
遠方から来た若年層の従業員に対応するため、昭和38年(1963)には「東浦繊維勤労青年学級」が開講された。
翌年には「東浦繊維高等学院」となり、さらに昭和41年(1966)には「東浦高等学院」へと校名変更された。
戦後の近代的な雇用形態とはいえ、従業員の多くは中学卒業直後の十代であり、雇用者が親に代わって社会教育や後期中等教育を施す必要があった。
そのため、国語・社会・音楽のほか、作法・料理・洋裁・和裁など多様なカリキュラムが設けられた。将来的な帰郷も視野に入れ、農業実習も組み込まれていた。
しかし、昭和40年代後半からの繊維不況と同じくして、生徒数も減少し、平成4年度(1992年度)をもって閉校となった。
生徒数
| 昭和38年 | 285人 |
|---|---|
| 昭和43年 | 566人 |
| 昭和50年 | 109人 |
|---|---|
| 平成4年 | 24人 |
(7) 今も残る大生紡績(たいせいぼうせき)工場跡
前述のように昭和30年~50年代には170軒ほどの工場が稼働していた。当時の生路には、大生紡績、前田紡績、長坂紡績、丸彦紡績、門田紡績、斉藤紡績などがあった。
大生紡績は、平成4年(1982)稼働停止したが、今も当時の事務所・工場や寮などが転用されずそのままの規模で残されている。もちろん古びた建物は今にも倒れそうな建屋もある。しかし、聞けば年に数回の撮影依頼や見学の依頼があるなど、産業遺産として脚光を浴びている。


引用・資料:東浦町誌