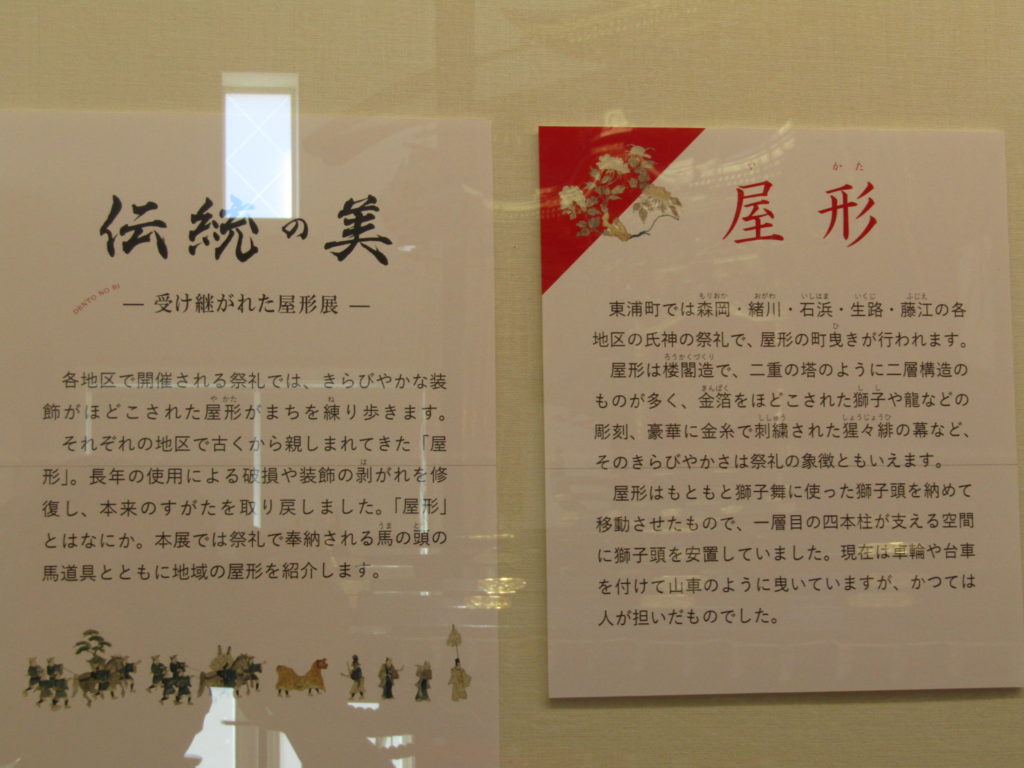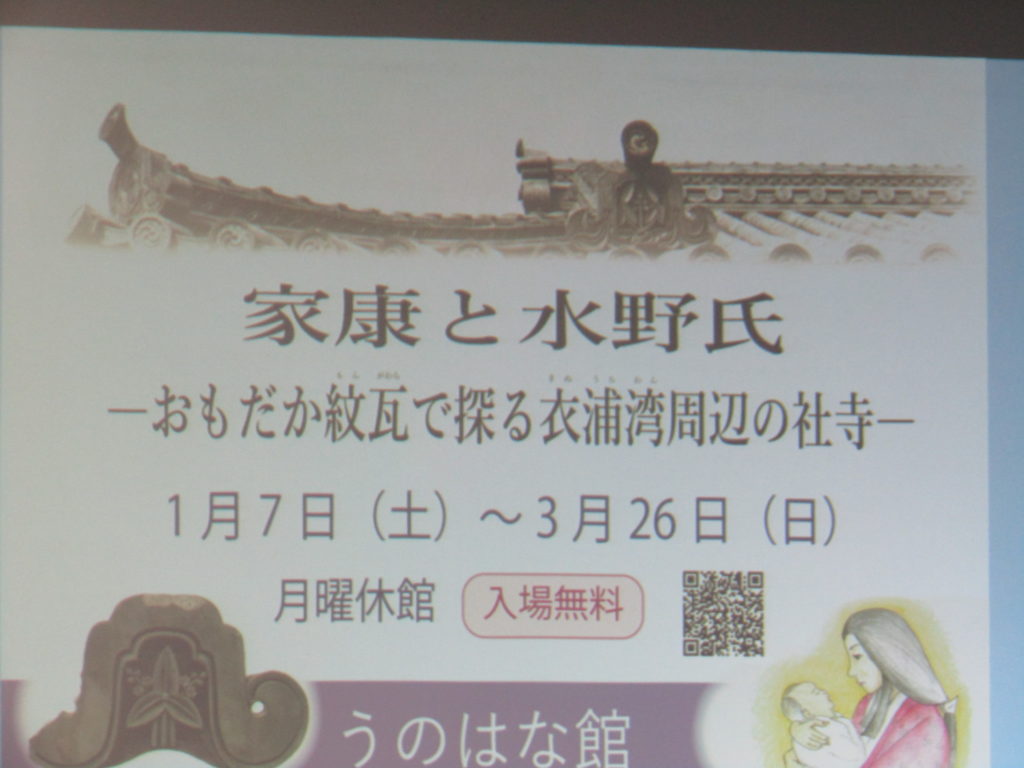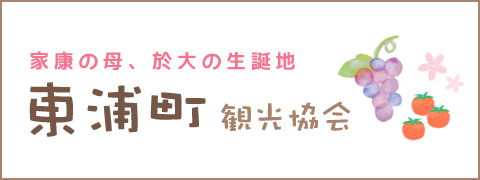5月18日 町の魅力再発見ツアー
2024年04月10日 : ふるさとガイド
再発見ツアーのご案内です。
信長が実戦で初めて鉄砲を使った村木砦の戦い跡を巡りませんか。
お申し込みは5月7日より観光協会へ、皆様のご参加お待ちしております!

とき
2024年5月18日(土)
集合:午前9時20分
集合場所
森岡コミュニティセンター
愛知県知多郡東浦町森岡杉之内15-3
コース
村木神社→村木砦跡→森岡コミュニティセンター(順次解散)
※スライドを使った説明をしてから出発となります。
定員
25名(先着順)
参加費(当日徵収)
200円
※ボランティア保険代、資料代など
主催
東浦町観光協会
協力
東浦町、ふるさとガイド協会
その他
・小学3年生以下は保護者同伴
・小雨実施
申込み
2024年5月7日(火)午前9時〜15日(水)午後5時の平日に問い合わせ先へ
問い合わせ
東浦町観光協会(勤労福祉会館内)
TEL:0562-83-6118